
PROGRAM
プログラムについて

子どもたちが楽しく学び、
元気に活動できる環境を
日頃からお子さまとの関わり方を迷われている保護者様の不安な気持ちは、いつのまにかお子さまにも伝わっているかもしれません。そのような保護者様の気持ちを丁寧にくみ取り、お子さまの特性に合わせた支援を行う場として「こもれびこども教室」を開設しました。
日々の教室では、楽しんで取り組めるプログラムとリラックスした状態で過ごせる環境を用意し、スタッフが一人ひとりのお子さまに対応します。お子さまとご家族の未来を見つめながら、ご一緒に一歩ずつ、進んでいきたいと考えます。


-
運動支援

マット・平均台・跳び箱・トランポリンなどを使用し、体幹や基礎運動能力を高める支援を行います。また、集団で活動することにより周囲を見ながら動く経験を重ね、お子さまのコミュニケーション能力の向上を図ります。
-
学習支援
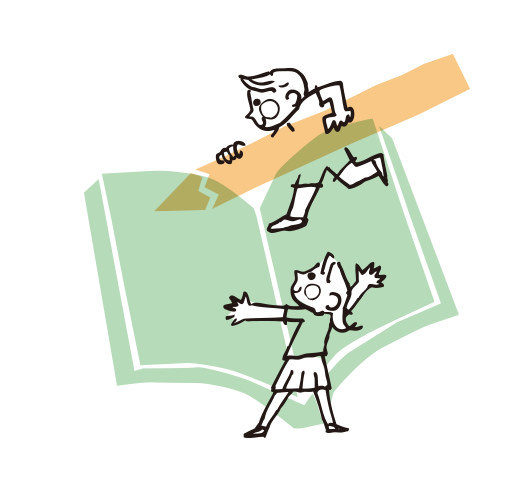
聞き取り、読み取りなどを通し、視覚や聴覚のトレーニングを行いながら、学習の基礎力の向上を目指します。座って学習する習慣も身につきます。また、運動と組み合わせることで学習効果を高めます。
-
専門性の高い支援
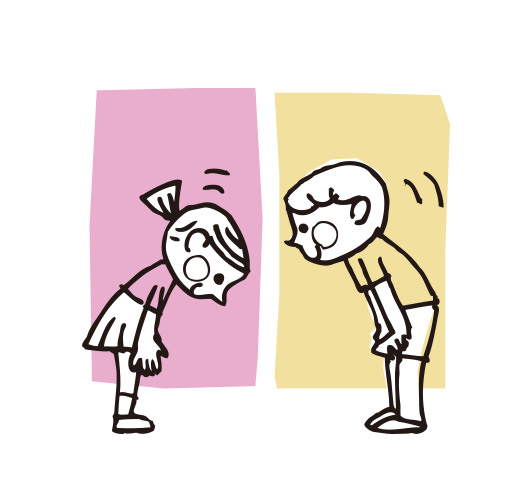
挨拶やお友達との関わりなどのスキルを身につけるソーシャルスキルトレーニング(SST)や生活面での自立支援など、専門性の高い支援を行います。「できること」を少しずつ増やしながら、お子さまの成長を促します。
-
個別支援相談

専門性の高いスタッフが入会時に面談を行い、お子さまの特性や課題を踏まえ、保護者様と一緒に支援計画を作成。一人ひとりのお子さまに合わせた支援プログラムを実行しています。
お子さまの成長に合わせた
環境を提供
きずなを深める
「2つの教室」
まずスタッフと個別のコミュニケーションを、次に2~3人のお友だちと、さらに10人程度の集団活動へと、環境に対するお子さまの成長過程を3つに分類。これらの環境を一人ひとりのペースに合わせて段階的に変えていけるのが、「こもれびこども教室」と「こもれびこども教室プラス」です。お友だちやスタッフと楽しく過ごす時間を増やしていきながら、人とのきずなを育むことができます。お子さまの社会づくりを一歩ずつ進めていきましょう。
こもれびこども教室

こもれびこども教室
プラス
個別
支援
- スタッフとの関わり
- ルールや約束を守ることを
学びます。
小集団
支援
- 2〜3人のお友だちとの関わり
- お友だちとの簡単なやり取りから、周囲への意識や関係性を学びます。
集団
支援
- 10人程度のお友だちとの
関わり - 集団での遊びやコミュニケーションから、他者への声がけや
自らの行動を経験し、学校など社会への適応力を学びます。

お子さまのバランスの取れた
成長を目指す
見直しながら
取り組む「5領域」の
プログラム
「発達支援(本人支援)」のうちお子さまの成長発達に関わる領域について、児童発達支援と放課後等デイサービスのガイドラインでは「5領域」が示され、総合的な支援が求められています。こもれび支援プログラムでは、この5領域すべてに取り組んでおり、一人ひとりに合わせた個別支援計画書を作成。お子さまの得意・苦手を判断し、成長や発達に合わせて適切に見直しを行いながら、サポートし続けます。

5領域
こもれび支援プログラムの主な取り組み
5領域/
こもれび支援プログラムの
主な取り組み
健康・生活
基本的な生活習慣を身につけ、健康な心と体を育みます。
- 食事
スプーンからお箸への移行や、お箸の正しい持ち方を練習します。 - 身の回りの整理
服の着替えやたたみ方の練習、靴下や靴の履き替え、トイレトレーニング、手洗い・うがいなどを身につけます。 - 学習の準備
自分で学習準備をする習慣を身につけ、自ら片付けやスケジュール確認を行い、家庭や学校での学習準備へとつなげます。
運動・感覚
姿勢や動作の基本を育み、視覚・聴覚・触覚などの感覚を高めます。
- 全身運動
ステップやジャンプなどで体幹を強くし、平均台やトランポリンでバランス感覚を掴むことで、姿勢保持にもつながります。 - 指先運動
鉛筆での書き取りやハサミの使用などを通じて、手先の細かい動きを身につけます。 - 視覚トレーニング
数字タッチや迷路、間違い探しなどの机上での活動を通じて、集中力や観察力を育てます。
認知・行動
環境や情報への適切な対応力を育み、園や学校、そして社会への適応に備えます。
- 社会適応力支援
カルタやボードゲームを通じて、困り事を解決する力や記憶力・集中力を高めます。 - 学習支援
物の名前や色の認知、数字や文字の読み書きの練習に取り組みます。 - 時間の認識
時計や工程表を使うことで時間の概念を学び、時間の使い方を理解し考える力を育てます。
言語・コミュニケーション
言葉の理解と表現を育み、コミュニケーションの基礎力を高めます。
- コミュニケーション
スタッフや他のお子さまと接する中で、日常的な挨拶や自己紹介を学び、会話のキャッチボールが続くよう練習します。 - 気持ちの相互理解
表情カードやお話づくりなどで、自分の気持ちを理解し適切に表現する力を育てるとともに、相手の気持ちを想像する力を伸ばします。

お子さま一人ひとりにあった
個別支援計画書の見直し
子どもたちに
質の高い支援の場を。
文科省は、1クラスに2〜3人程度、特別な支援が必要な子どもたちがいると発表しています。特別な支援は、もう特別なものではなくなってきているのです。お子さまのためにも「児童発達支援」や「放課後等デイサービス」の活用は、大きな意味があると考えます。個の発達や課題に応じた細やかな支援ができる環境が整っており、専門的な知識を持つ職員に長期的な視野で教育や進路を相談できます。その結果、保護者さまにゆとりが生まれ、お子さまを肯定的に見ることができるようになるでしょう。また、これらの場が支援の基地的機能を果たし、総合的な支援へとつなげていくことも可能です。
「こもれびこども教室」は、このような取り組みを実践し、お子さまの可能性を伸ばす質の高い支援を目指しておられます。私たち「(一社)障がい児成長支援協会」も積極的にサポートしてまいります。
学校心理士・
ガイダンスカウンセラー
一般社団法人
障がい児成長支援協会代表理事
山内 康彦氏
1968年3月30日生まれ
岐阜県教員や教育委員会などでの勤務を経て、岐阜大学大学院教育学研究科(教職大学院)で学び、小中高・特別支援学校の専門職修士となる。現在は「一般社団法人・障がい児成長支援協会」の代表理事として学会発表や講演会など積極的に活動。現場目線で具体的な解決策を提案する講演会は各地で好評を得ている。『「特別支援教育」って何?(WAVE出版)』『体育指導用教科書(学研)』など著書多数。



社会福祉法人
大阪誠昭会が運営する
認定こども園・
保育園との関わり
私たちが運営する認定こども園・保育園と連携したインクルーシブ教育・保育により、障害の有無や年齢などにとらわれずに、お互いを認め合うための機会をつくっています。戸外あそびでは認定こども園の整備された園庭も利用するなど、より安全な学びの環境を整えています。

デイリープログラム
主に個別・小集団での活動
| 時間割(Aクラス) | プログラム内容 |
|---|---|
| 13:00〜17:00 上記時間内で1時間程度の支援プログラム |
順次通室 ご自宅(幼稚園、保育園、こども園)から車での送迎がご利用できます。 
自由遊び 教室に到着し、準備ができたら教室内で遊びます。 運動支援 身体を動かし、基礎運動感覚を養います。 学習支援 視覚や聴覚の基礎力がつくよう、楽しんで取り組みます。 
順次送迎 ご自宅(幼稚園、保育園、こども園)へ車での送迎がご利用できます。 |
| 時間割 (Aクラス) |
プログラム内容 | ||
|---|---|---|---|
| 13:00〜17:00 上記時間内で1時間程度の支援プログラム |
順次通室 ご自宅(幼稚園、保育園)から車での送迎が利用できます。 
自由遊び 教室に到着し、準備ができたら教室内で遊びます。 運動支援 身体を動かし、基礎運動感覚を養います。 学習支援 視覚や聴覚の基礎力がつくよう、楽しんで取り組みます。 
順次送迎 ご自宅(または、幼稚園、保育園)までの車での送迎が利用できます。 |
||
主に集団での活動
| 時間割 | プログラム内容 |
|---|---|
| 13:00〜15:45 |
順次通室 ご自宅(小学校・学童)からの送迎が利用できます。または徒歩で通室することも可能です。 
自由遊び 教室に到着し、準備ができたら教室内で遊び、友だちとの関わりを学びます。 |
| 15:45~18:00 |
おやつ 友だちと楽しくおやつの時間を楽しみます。 
運動支援 身体を動かすことで運動を支える基礎感覚づくりを行い、学習に入る準備をします。 
学習支援 視覚、聴覚、知覚の基礎力がアップする学習支援を行います。 |
| 18:00 |
順次帰宅 各自帰宅します。 |




